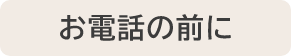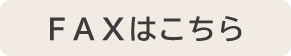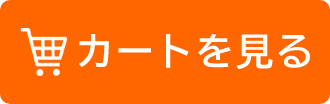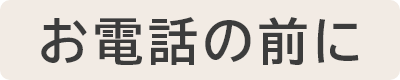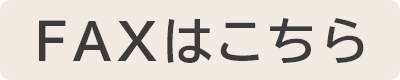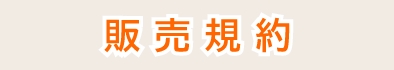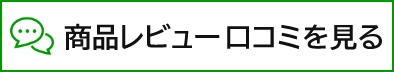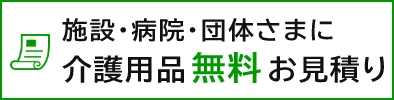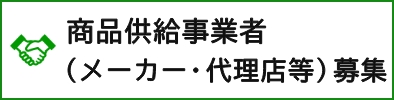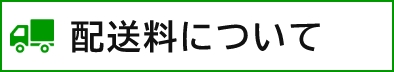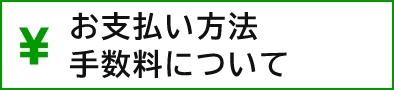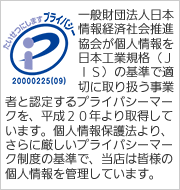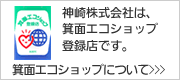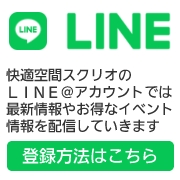| 絵画療法 |
絵を描いたりして心の状態を表現することですすめる治療。 |
介護アテンドサービス士 |
介護能力の高い家政婦のこと。体位変換、食事の世話、排泄の介助、寝巻の交換、移動補助などの介護をしたり、一般家庭などにおいて、寝たきり老人のの介護を行う。 試験により厚生労働大臣から認定される。 |
介護一時金 |
有料老人ホームに入居者が支払う費用のこと。入居時に支払う介護一時金払いと、介護が必要になってから支払う二つの方法がある。 |
介護者慰労金 |
介護福祉手当を受けている在宅の高齢者を常時介助している人に支給される報償。 |
介護保険制度のもとで、要介護状態と認められた被保険者が受け取る給付のこと。(つまり要支援では受け取れない) 以下の9種類の保険給付に分けられる。
|
|
介護給付費 |
介護給付によって支払われる費用。 |
介護支援サービス計画の通称。別称:ケアプラン。 |
|
介護サービス調査票 |
介護保険制度のもとで、要介護度の1次判定を行うために使う調査票。マークシート式で介護認定調査員が記入する。大きく分けて概況調査、基本調査、特記事項の3つの項目がある。 |
介護保険制度のもとで、在宅サービスを利用する場合や現物給付をうけるために作成する計画。通称:ケアプラン。介護支援専門員(ケアマネージャー)が作成するほかに利用者自身でつくることもできる。 |
|
介護支援専門員 |
通称:ケアマネージャー |
介護実習普及センター |
「高齢社会は国民全体で支えるもの」という考え方を地域住民に啓発することを目的に福祉用具の展示や相談をおこなうところ。 |
階段昇降機 |
階段の昇り降りが困難な人が、階段を安全に昇り降りするための機械。 階段にレールを敷いて、椅子や人・車椅子を乗せれるトレイなどがそのレールに沿って移動するものと、手動でオペレーターが操作しならが階段を昇降するタイプがある。 |
介護専用型有料老人ホーム |
入居時から介護を必要とするひとが入居する老人ホーム。 |
要介護度の通称 |
|
介護認定審査会 |
介護保険制度のもとで、被保険者が介護保険の対象になるのかどうかの要介護認定をおこなう組織。原則として市町村ごとに設置される。医師、看護師をはじめ、医療、保険、福祉の分野で高齢者介護に携わっているひとたちが任命されている。 |
介護認定調査員 |
介護保険の支給対象者となるかどうか認定の判断材料を集めるため、申請者を訪問する調査員のこと。 |
介護福祉士 |
専門的な知識と技術をもって、身体上、精神上の障害のために日常生活を営むのに支障があるひとに介護を行い、本人や介護者に対して介護に関する支援や指導を行う専門職。社会福祉士及び介護福祉士法に基づく国家資格を有した専門職。 |
介護福祉施設サービス |
寝たきりや痴呆性老人のための施設、特別養護老人ホームで日常生活の世話など受けることができる。介護保険では自分で好きな施設を選ぶことができる。 |
介護扶助 |
生活保護法で定められた扶助の1つ。生活保護を受けているひとが介護保険制度を利用して介護サービスを利用した場合、以下の介護サービス利用料金が介護扶助として支給される。 |
介護報酬 |
介護保険制度のもとで、介護サービスを提供した者が得る報酬。 |
介護保険事業計画 |
介護保険に必要な基盤整備と運営のために、自治体がさだめる計画。 |
介護保険施設 |
介護保険法に基づく、施設サービスを提供するところ。 |
介護保険審査会 |
介護保険のサービスをうけるひとが、その内容に不満がある場合に、不服を申し立てるところ。都道府県ごとに1つ設置される。 |
介護保険単価 |
介護保険で提供される各種サービスの単価のこと。サービスによって、時間単位であったり、日単位であったりする。 |
介護保険の3施設サービス |
介護保険で供給されるサービスのうちで、次の3施設は介護保険の3施設サービスと呼ばれることがあります。 特別養護老人ホーム 指定介護老人福祉施設【施設サービス】 |
介護保険法 |
介護が必要になったひとに、保健医療サービスや福祉サービスに関する給付を行うために1997年12月に制定され、2000年4月施行された法律。 |
介護利用型軽費老人ホーム |
通称:ケアハウス 自炊ができない程度に、からだの機能の低下したひと、または高齢等のため独立して生活するには不安があるひとで、家族の援助を受けることが困難な場合に入所する施設。 |
介護療養型医療施設 |
介護保険施設の資格がある医療施設。療養型病床群(病院と有床診療所)、介護力強化病棟、認知症疾患療養病棟のうち、介護保険適用申請を経て指定された病棟(病室の場合もあります)が指定介護療養型医療施設といわれます。 |
介護療養施設サービス |
要介護のお年寄りが指定介護療養型医療施設に入院して受ける介護サービス(一定の医療サービスも含まれます)。 |
介護力強化病院 |
別名:入院医療管理料承認病院 |
介護老人福祉施設 |
指定介護老人福祉施設や特別養護老人ホームとも言う。 |
介護老人保健施設 |
老人保健施設とも言う。 |
介助ブレーキ |
介助者が、走行中に速度を調節するためのブレーキ。 バンド、ドラム式、ディスク式、駐車ブレーキ連動式などがあります。 |
疥癬 |
疥癬虫というダニの一種が寄生によって起きる伝染性の皮膚病。激しいかゆみがある。 |
ガイドヘルパー |
guide helper 単独で外出することが困難な障害者などが外出する場合に、時の付き添いを専門に行うヘルパーのこと。 |
回復期リハビリテーション |
差し迫った生命の危機から脱し、負荷を大きくしても可能な時期になったとき日常生活動作の改善を期待して行われるリハビリテーション。 |
回復力 |
疲労や傷病から元にもどろうとする力。 |
ガウンテクニック |
gown technic 感染を予防するためにガウンを使用する方法で、そのガウンの着脱の手順をいう。 |
地域で開業し市民の日常的な医療相談、診察に応じる医師のこと。別称:家庭医 |
|
かかりつけ医意見書 |
介護保険制度で、介護認定審査会が2次判定を行うとき用いる意見書。かかりつけ医が作成する。 |
介護保険制度のもとでは、高齢者に対して、入浴、排せつ、食事などの介護のほかとして、調理、衣類の洗濯や補修、住まいの掃除、生活必需品の買い物など日常生活を送る上で欠かせない家事援助サービスのこと。 |
|
家事援助サービス |
家事援助の項を参照のこと。 |
学習障害 |
中枢神経系の機能障害を有するために、聞く、話す、読む、書く、推論する、計算するなどの学習に関する能力の習得や使用に著しい困難を生じること。 【略称】LD、learning disability |
学童保育 |
放課後帰宅しても保護者がいない場合や、病気などで適切な監護ができないなどの場合、小学校低学年の児童に対して、児童館、保育所、学校の空き教室やを利用して、児童の健康増進、情緒の安定や創造性の向上などの目的で行われる保育対策のことをいう。 |
下肢障害 |
股関節、大腿部、膝関節、下腿部、足関節、足部のことを下肢といい、歩行などの移動能力や立位、座位などの姿勢維持などの障害のことをいう。 |
家事援助 |
掃除、洗濯、調理などの日常活の援助をさす。 |
家具調トイレ |
室内の置いても違和感の無い木製のポータブルトイレです。 |
過剰介護 |
本人でできる能力があるのに、時間がかかるなどの理由で、必要以上の介護をしてしまうこと。 |
仮性痴呆 |
器質的な脳障害がないにもかかわらず、認知症の症状を呈する状態。意識障害やうつ病の時に見られることがある。 |
家政婦 |
「看護師・家政婦等職紹介所」などに所属し、そこからの紹介によって私的契約を結び、病人や障害者の世話や家事援助を行うことを目的とする職業。 |
家族介護者教室 |
寝たきりや痴呆などで介護が必要なひとを家庭で介護する家族を対象として、介護に必要な知識や技術を与え、介護者同士の交流をはかることを目的とした講座のこと。 |
片麻痺 |
体の片側のみに運動機能障害が出ること。脳卒中に伴う障害として多い。 |
課題分析 |
事前評価、アセスメントともいう |
課題分析票 |
アセスメント票 |
活動的平均余命 |
active life exectancy 身体の基本的な日常生活動作(ADL)指標で測定された年間のADL低下率である「非自立者率」を用いて、ある年齢区分にいる人があと何年自立した生活を送ることができるのかを表したもの。 |
カテーテル |
catheter 尿、血液、体液の排出または治療薬を入れたりするための柔軟性のある管のこと。 |
家庭医 |
かかりつけ医 |
過程記録 |
ケースワークの過程で、ケースワーカーと相談者の関係を、時間的経過に従って書いた記録のこと。 |
カニューレ |
cannula 様々な大きさの人工的なチューブで、体腔内に挿入するものを指す。介護場面では、気管カニューレを指すことが多い。 |
下半身麻痺 |
麻痺が臍部周辺(おへそのあたり)から下部に及ぶ場合をいう。 |
加齢 |
年齢を加えていくこと。歳をとること。 |
眼瞼下垂 |
上のまぶたが意志に反して眼球を覆っている状態。 |
感情失禁 |
自分の感情をコントロールできず、わずかな刺激で泣いたり笑ったり怒ったりしてしまうこと。 |
関節可動域訓練 |
本人あるいは介護者によって、動かせる範囲で関節を動かしていくこと。 |
感染症 |
ウイルスなど病原体が生体に侵入し、増殖することで起きる病気の総称。HIV、結核、マラリアは三大感染症と呼ばれる。高齢者の感染症の特徴は、発熱、せき、たん、息切れなどの感染症に典型的な症状が生じるとは限らないことである。 |
感染予防 |
感染症になることを防ぐこと。感染予防の3大原則は以下の通りである。
|
患側 |
身体機能に何らかの障害が生じている場合、体を右と左に分け、障害がある身体側のこと。麻痺側ともいう。 |
乾熱ホットパック |
温熱療法のうちで、伝導熱を用いて治療する器具、もしくはその方法をいう。似た療法に温熱ホットパックがある。詳しくはホットパックの項を参照のこと。 |
寒冷療法 |
患部を冷やすことで炎症を抑え、痛みや筋肉の緊張をやわらげること。 |
カンファレンス |
conference 会議、協議、打ち合わせのこと。 |